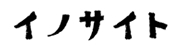現象学のまなざしで職場を捉えてみる
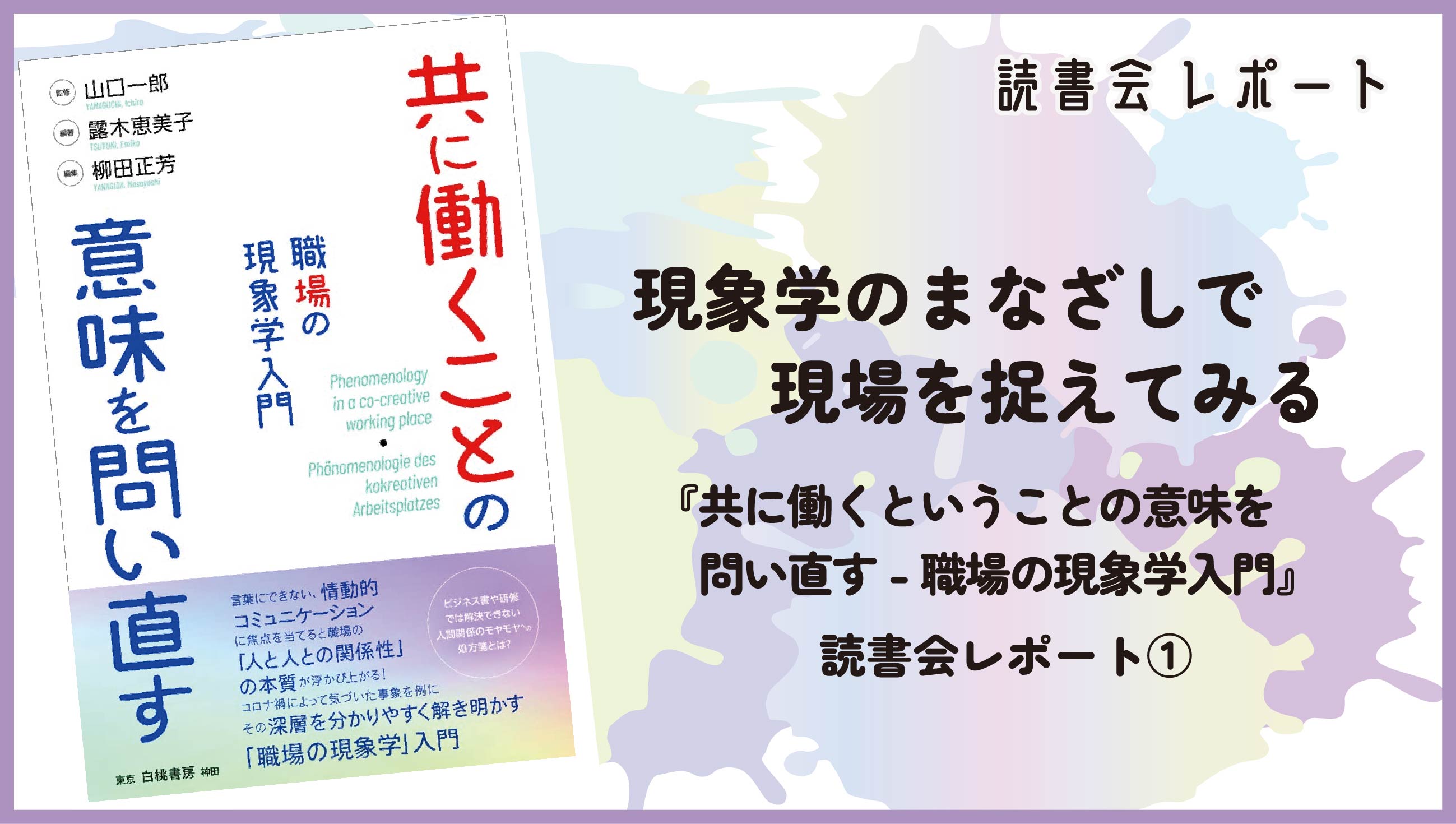
『共に働くということの意味を問い直す 職場の現象学入門』 (露⽊恵美⼦ 白桃書房 2022)
読書会レポート①/ 土谷真喜子
『職場の現象学入門』の読書会は、初回に露木先生をお迎えして、社労士として日々企業の課題に取り組まれている参加メンバーに対して、露木先生から「働くことの意味と問う」ということの魂を授けられてスタートしました。

矢萩さんが先生を発見し、リスペクトされて追っかけ(!)をされてきたことに深く感謝します。奇しくも露木先生とは大学の同窓であることがわかり、私が卒論指導を頂いた社会学の石川晃弘教授の大切なお弟子さんでした。

そして長年ご無沙汰していた石川先生にもこの出会いをご報告することができました。自分の中で、社会学を学びながらも経営学の実践的なアプローチに憧れ、組織開発の周辺をうろうろしてきたことが、ぐるっと一周回ってつながった感覚に不思議なご縁を感じています。

読書会は、毎回チェックインで小グループに分かれての近況報告から始まります。それぞれ仕事や遊びや学びのエピソードを持ち寄って語りあう時間です。背景の写真も多彩で個性的、参加の楽しみとなっています。そこから読む時間を少々頂き、読書会に向かう心の準備を整えます。(この時間、あわててzoomに入った時など助かっています)
ここから読書会が本格スタートします。毎回、各章の概要についてのガイドを頂き、その後でグループ・ディスカッションを行います。このガイド&ディスカッションの方法は、準備不足の身にとってはありがたく、自分が読みたいように読んでいたことの狭さを反省しつつも、ディスカッションで自由に議論をする共通の土台を頂くことができます。

以下、各章を通じて感じたことをまとめます。
〇第1章 悩める職場のコミュニケーション
本書では、特にこの30年間我々が経験してきたインフォメーション&コミュニケーション技術(ICT)による職場の変化について着目しています。オンラインの仕事とリアルな仕事の狭間で翻弄される働き方を現象学的な視点からどうとらえるか、ということにチャレンジする章です。私は、キャリアコンサルタントの仕事をしているので、個人の視点から働くことや会社の在り方、環境について、日々考えさせられています。転職を希望する人が、リモートワークで、年収も上がって、やりがいもあって、自分が成長できる仕事をしたい、とおっしゃることを聞きながら、それを受け止めてくれる会社はあるのだろうか、どうやって自分の能力をわかってもらうのか、どうやって会社の人と信頼関係を築くことができるのだろうか、と疑問が浮かんでくるのです。
この章で印象的な言葉として「正解依存症候群」があります。正解だけがあれば、管理しやすいという志向のもとには、余白も失敗もなく、個人としても組織としても器は小さいままなのではないでしょうか。そこには、同じメンバーと技術でイノベーションを起こすチャンスやチャレンジは生まれないので、別の会社をM&Aして、ブロックをつなぎ合わせたような新規事業でやったつもりのアピールをすることになってしまうと思います。そしてそこも正解依存症で運営するといる循環になりそうです。この悪循環を突破するためには、生産性だけでなく創造性を価値として据えることが必要です。その創造性はリアルな身体による対話から生まれるものなのではないか、ということに気づかされます。人間の身体こそが、過去と未来を行き来して、さまざまな他者との経験を通じて、感じ、振動しながら生きて働くものなのだということを考えていきたいです。

〇第2章は、職「場」とは何か?
日本語の「場」という言葉について、露木先生が海外の方に聞いたところ、そういった概念を意味する英語はないと言われたというエピソードが記されています。単なる場所だけでなく、雰囲気や目に見えない関係性が入っている「場」というものだからこそ、日本の「職場」の構造は複雑で一筋縄ではいかないものなのかもしれません。会議の雰囲気は、そこで行われる議題の内容や言葉だけでなく、目に見えない「情動的コミュニケーション」が大きな影響を与えているということ、なんとなく感じていましたが、安心感とか違和感とか、心地よさとか、そういった様々なものが、ひとつの空間の中に存在しているということは自覚していませんでした。このことを「暗黙知」という言葉で表現し、対する言語的なものを「形式知」として、その相互作用によって「場」がつくられているのです。
そして会議だけでなく、職場においても日々、暗黙知と形式知が複雑に絡み合い、日本独自の特徴があることについて、この章でディスカッションすることができました。
特に日本の職場におけるパワハラや過労死、メンタル不全、自殺など、すさまじい状況については、「ハイコンテクスト社会」という閉鎖的な関係性に基づいているということが示されています。日本社会では、言葉の受け取り方や解釈に想像力を働かせて察っすることを求める傾向があり、それによって受け止め方で行き違いが生じてしまうのです。ハイコンテクストが意味するところは「文脈が複雑で密である」という意味であるため、言葉に無責任である面も否めないように感じました。グループ・ディスカッションの中で、「当事者意識は身体で感じるものなのではないか」ということについて語り合い、フルリモートでの仕事だと、うつ病になり易いという傾向について、今後変化の中で若い人達を今後どうサポートすべきか、などの話題が出ました。
〇第3章は、なぜ、いま「現象学」なのか?「現象学」とは何か?
前2回の講座を踏まえて、第3章では、現象学が何を扱っているのか、ということを
考える時間となりました。本書に、〈現象学とは、私たちが日々職場のなかで感じていることや考えている事の「根っこ」に何があるのかを体系的に考える哲学です。〉と記されています。現象学は、物事の見方の構造や働きについて着眼し、思考する取り組みなのだと理解しました。だからこそ、30代での感じ方と60代の感じ方は異なるし、時代によって、立場によって、さまざまな見え方があるのかもしれない。答えは一つではない、ということが前提とされているのではないかと思います。
キャリアコンサルタントの仕事は、傾聴することを日々求められますが、それが得意になっていくかというと、まったく逆で、日々反省の繰り返しです。何故なら、相談者の年齢、性別、職種、所属、経歴を聞けば聞くほど、自分の中の「判断」事例がムクムクと湧き上がってきて、この人はこうなんだ、と本人に言わないまでも内心思い込んでしまうのです。そこを「判断停止」させて、フラットな状態で受け止めることの難しさ。頭ではわかっていてもなかなかできていないので、〈現象学の基本的な考え方を理解すると、職場での悩みが「なぜ生まれてくるのか」「どうしてそういうことが起こるのか」を理解できると思います。〉という一節は身につまされるものでした。グループ・ディスカッションの共有の時に、判断しない、無意識で聞くことによって、
インナーソース同士が結びついて本当にエネルギーが出て、思い込みのない世界になる、
というコメントが心に残りました。
さらに、「我とそれ」の世界から「我と汝の関係」に突き抜けていく感覚の大切さについては、ラグビーやブラスバンドの経験など、それぞれの人の持つ共通感覚について、改めて思いを巡らしました。人との関わりだけでなく、自然や街や歴史的空間とも「我―汝関係」を感じることができるという思いは、日光街道を歩いてみたからこそ得られたものかもしれないです。そして個人的には、空手の型を一生懸命やっていた時もそういう感覚を得ていたような気がしています。今後もたくさんの「我―汝関係」を実現していきたいものです。
グループ・ディスカッションの共有の時に、判断しない、無意識で聞くことによって、
インナーソース同士が結びついて本当にエネルギーが出て、思い込みのない世界になる、
というコメントが心に残りました。
さらに、「我とそれ」の世界から「我と汝の関係」に突き抜けていく感覚の大切さについては、ラグビーやブラスバンドの経験など、それぞれの人の持つ共通感覚について、改めて思いを巡らしました。人との関わりだけでなく、自然や街や歴史的空間とも「我―汝関係」を感じることができるという思いは、日光街道を歩いてみたからこそ得られたものかもしれないです。そして個人的には、空手の型を一生懸命やっていた時もそういう感覚を得ていたような気がしています。今後もたくさんの「我―汝関係」を実現していきたいものです。

毎回、最後にAIげんさんとの対話の時間を持てることも、この読書会の魅力です。げんさん、なかなかほめ上手で、質問心をソソッてくれます。私は、チームや組織での仕事から離れているので、30年くらい前のデザイン事務所時代のあれこれを相談しました。いろいろな出来事で行った自分の選択、よかれと思ってやったことがうまくいかなかったことなど、げんさんに質問しようと思うと、受け身ではなく能動的に考えることができます。そしてげんさんは、「でも」とは決して言わず、絶対に受け止めてくれて、プラスして他の見方などを投げかけてくれるのです。これが日々のコンサルティングでできないんだよな~と思いながら、げんさんの見識の広さに質問が止まらなくなる自分がいます。
次回、最終回もよろしくお願いします!