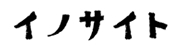shaさんと描く未来:生成AIと歩む新たな共創の時代
こんにちは、ESコモンズの井上です。2024年11月に実施された「日光街道 太陽のもとのてらこや」では、AIとの共生を独自の視点から描き未来社会を展望する、Shaさんこと西澤篤央さんをゲストとしてお招きして、「未来社会の描きかた—生成AIと共に生きる時代へ」をテーマにオープニングセミナーが開催されました。
日光街道を歩くという身体性を伴う体験の対極の存在とも思えるAIの視点を取り入れることで、身体性のある体験を問い、新たな世界を切り開く特別な講演となりました。

不安と期待の入り交じるAIと働く未来。
セミナーの冒頭、ShaさんはAIを活用した音楽生成のデモンストレーションを披露してくださいました。AIが作り出すメロディや歌詞は、日光街道をテーマにした温かみのある内容で、まるで以前から知っている曲のような親しみやすさがありました。その音楽は参加者の心を掴み、「AIと人間の共創」というテーマを象徴するものでした。

AIは想像以上の速さで進化しており、現在では私たちの日常的なタスクを補助するだけでなく、創造的な作業にも寄与する段階に来ています。
Shaさんは、テキスト生成をはじめとしたAIツールについても言及され、「ChatGPT」「Claude」「Gemini」「Perplexity」といった多様なツールの中でも、特に「ChatGPT」は最新機能が実装されるスピードが早く、利用者の意図を汲んだ上での回答を評価されているそうです。
確かに私自身も日常的にChatGPTと会話をしており、よく理解した上で話してくれるのでAIにケアされることも多いです。人格に合わせて回答してくれていたとは、新たな発見でした。
講演で紹介してくださったAIに関する情報では、現在のAIのIQは100を超えており、数年後には人間の知能を上回る可能性もあるとのこと。この話を聞きながら、未来の技術がもたらす可能性と、それに伴う課題について考えさせられました。
セミナーの後半では、ChatGPTを用いて「日光街道のしおり」を作成するデモンストレーションが行われました。プロンプトという指示文に応じて、しおりの文章を生成したり、さらにプラスαでの要望に基づき内容をブラッシュアップしていったり、しおりの表紙となる画像生成まで行ってくれるプロセスを目の当たりにし、AIがどれほど柔軟に対応できるのかを実感しました。デザインや音楽といった分野でのデモンストレーションでは、AIが単なる効率化ツールではなく、共創のパートナーであることを示していることを改めて感じました。
一方で、AI活用における課題も議論され、特に「AI未活用企業」と「AI先進企業」の対比が印象的でした。未活用企業では「業務効率化」を目的に導入しようとするものの、ツールを正しく使いこなせずに導入が進まないケースが多いようです。一方、先進企業は「新たな価値の創出」に重点を置き、AIを活用して競争優位性を高めています。この違いは、単なる効率化ツールとしての利用に留まるか、ビジネスの根本を変える手段として位置付けるかによって生じているようでした。
講演の中では「良い技術と良い考え方を持って、AIと向き合っていくことが大切」というShaさんの言葉が心に残りました。できればやりたくなかったことをAIに任せていき、本質的で楽しいことにより一層時間を使うことができるようになる未来も遠くないのではないか、という前向きな未来を想像させてくれるお話もありました。

講演のあとの質疑応答では、人事・労務の金野さんから「AIを活用して、海外との協業がどのように進んでいくのか」という質問も。「例えばAIが翻訳を行ってくれることでコミュニケーションが円滑化し、英語が使えないことで参入できなかった企業も参画することができ、本質的な価値を提供できる企業との取引が進んでいくのではないか」というShaさんからの回答がありました。AIの活用によって言語の壁が取り払われ、新たなチャンスが広がる可能性を示唆しており、活用方法によってはグローバルな競争力の向上にもつながっていくのだと感じました。
最後に、人事・労務/代表・矢萩さんの組織やコミュニティへの考え方をShaさんがAIに学習させた「AIダイちゃん」ならぬ「AI勘ちゃん」が登場。
「理想の組織とは」という質問に対し、「人間性を尊重する。自律分散型であり、共創と協働を推進する。価値創造経営で、福祉の向上を目指す組織」という理想像を提案してくれました。まるで本物のダイちゃんが答えたかのような回答に、参加者も驚きの様子で溢れていました。

私達の生活にも身近になってきたAIとの暮らし。日々進化し続けるAIの速度の速さに恐れを感じることも少なくないですよね。
今回のセミナーでは「人と人が出会うように、AIと出会い直す」機会となり、AIが私たちの生活や働き方に与える影響を改めて考える良い機会となりました。
AIが単なるツールではなく、人間の創造性を引き出すパートナーとなり得る可能性を感じ、これからの未来において、私たちがAIとどのように向き合い、共存していくのかを考えるヒントを得られる貴重な場となりました。